東京都内での激しい経済格差
東京都内でも激しい経済格差があった
今でも日本には経済格差があります。
元々は日本は「皆中流」みたいに長いこと言われていましたがバブルがはじけた辺りからなのかかなりの差が出てきています。
世界的には普通のことなのでしょうが、日本は非常に長い期間そういうことはあまりなかったので決してよいことでは無いと思います。
だって「皆平等」で社会が作られてきたので急に格差社会になったら追従できなくなるのは当然です。
よく新聞記者が単にネタのために「日本のやり方はガラパゴスでよくない」という記事を書きますが、これは真剣にそう思っているのではなくて単純に記事を増やすための姑息な手段に過ぎません。
国によって情勢が違うのだからガラパゴス化大いに結構だと私は思っています。
輸出大国である日本はガラパゴス文化と言っても輸出時は国ごとに細やかに対応して来たのですしね。
さてそんな格差が無いと思われていた経済成長真っ只中の1960年代は実は経済格差が今よりもはるかに大きい時代だったと思います。
大人(おっさん)になった今改めて思うだけではなく、小学校低学年の時でさえその格差を私は感じていました。
幼少期に感じた格差
私の幼少期とは1960年代となります。
当時杉並~練馬に住んでいて、小学校は5年生1学期までは練馬区でしたが経済格差はかなりあったと思います。
例えば当時を振り返ると以下のようなものがありました。
・住居の形態
一軒家か賃貸かというレベルではなくて、賃貸であっても「都営/公団アパート」と民間アパートではやはり前者の方がワンランク(それ以上?)上と言うイメージがありました。
実際のところこれらに住んでいた各家庭の所得はわかりません。
しかし民間アパートでも現在のような「おしゃれで綺麗で広く」という物件が無かった時代でしたので「民間アパート=狭い、ボロい、かっこ悪い」というイメージだったと思います。
ですから都営/公団に入れない、もしくは抽選に漏れて止むおえず民間アパートに、という人が多かったのではないでしょうか?
また一軒家に見えて実は民間アパートという物件も多く、そういう家は殆どが世間で言う長屋という感じでした。
悪い言い方をすると戦後の混乱期に住居の数を確保するために急遽作られたような家です。
もちろん当時でもそこまで古いものは殆ど無かったと思いますが、最近用事があって幼少期に住んでいた場所を訪れてみると当時の長屋(のような家)がそのまま残っていて人が住んでいるのには驚きました。
・子供の服
当時は全然気にも留めませんでしたが後で思うと服でも経済格差があったと思います。
1960年代の高度経済成長時代ですので全国何処に行ってもみすぼらしい格好をしている子供などは殆どいなかったと思います。
今の時代であっても貧しい開発途上国などは子供が裸足で生活している、穴が開いてボロボロの服を着ているなんてテレビで見ることがありますが、1960年代の日本ではあり得ないと思います。
しかし服による差もあったと思います。
金持ちの子供が特別に良いとか綺麗な服だったと言うのではありません。
これは100%私の個人的感想ですが中流以上、もしくは豊かではないけれど子供には良くしてあげたいという気持ちが特に強い親は普段でも子供にブレザーを着せたり、同じ服を繰り返し着ないようにさせていた感があります。
・車の所有
これは圧倒的に親の経済力を反映していたと思います。
当時は高度経済成長ということもあって幹線道路には車が溢れ、テレビでも新車のコマーシャルがたくさん流れていました。
つまり景気の良い時代だったのです。
(当時はスバル360やコロナマークⅡなんかもたくさん走っていましたね。)
住宅街でも路駐の車もたくさんみかけましたし、子供たち(男の子)の話題も新しく発売された車の話しも多かったです。
しかし・・・、家に車がある家はまだまだ少なかったと思います。
高所得者は当時も車の所有率は高かったと思いますし、一軒家でそこそこ大きな家にはたいてい車がありました。
東京23区内だったので今でも無理して車を所有することもない場所ではあるのですが、普段の生活に追われて車どころではない家庭が多かったのでしょうし、今のように誰でも運転免許を持っている時代でもなかったのです。
(私の両親も運転免許は持っていませんでした。)
軽自動車や中古車でも「とてもとても買えない・・・」というのが平均的な庶民の生活だったと思います。
・科学と学習
学研の「科学と学習」という教材付きの本を月に一度学校の校門付近とかに売りに来ていました。
(黄色い半透明のビニール袋に本を入れてくれました。)
これらの本は書店では売っていないのです。毎月買っていた人も数多くいたと思います。
また小学館の「小学○年生」という本も子供たちには大人気でしたね。
こちらは書店で購入する本ですね。
ところがこれらを買えない家庭の子供が一定数いたんです。
また買えても「科学だけ」、「学習だけ」とか片方のみを買ったりする子供もいました。
(その月の付録によってどっちを買うかは決まっていなかったようです。)
実は練馬区の小学校に通っていた時に、校門前で販売される「科学と学習」の事がPTAで問題になったのです。
理由は「買えない子供がかわいそう」というものでした。
当然だと思います。今や人様の親になった私としては子供がそんな思いをしたら自分自身涙が溢れてしまいます。
さらに当時その小学校には児童養護施設から通ってくる子供もたくさんいたのです。
そういう子供たちはまずこれらの本を買うことが出来ません。
私も子供心に彼らに申し訳ない気持ちで「科学と学習」を求めていました。
そしてPTAからの提案などによりある時に販売場所が変更されたのです。
校門前ではなくて学校から程近い一軒家のお宅の玄関で売られることになりました。
そのご家庭には多分子供がいて私と同じ小学校に通っていたのでは、と思います。
これで校門前で売られることはなくなりました。
もう1つの「小学○年生」ですが、こちらは書店のみでの販売なので問題なさそうですが、でもたまたまある月の付録が特に面白かったりすると学校でその付録の事が話題になるのです。
そうすると買えない子供は黙って聞いているだけ、ということになってしまいます。
私は学校でなるべくこれらの話題には触れないようにしていました。
・練馬と新宿の子供の違い
先に述べたように小学校5年生の2学期からは新宿区の小学校に転校しました。
最初に住んでいたのは練馬でも西の外れの上石神井でしたからはっきり言って田舎でした。
転校した直後は特に格差を感じず(練馬と比べても)友人との毎日を堪能していました。
先に述べた「科学と学習」の販売場所は正門や個人宅ではありませんでしたが、正門からほど近いある「お屋敷」の玄関前の広場?で売られていました。
新宿と言っても練馬と比べて特別に子供の服が綺麗だとか、持っているもの(カバンやおもちゃなど)のランクが上だとかは感じませんでした。
あえて言うならば場所柄ということでしょうが、「親が水商売で片親(母のみ)」、「家が飲食店経営」のお宅がかなり多かったですね。
練馬西部よりは各家庭の所得は高かったかもしれませんが、山手線の内側という大都会でしたので車を保有している家庭は少なかったと思います。
買ったところで土地が無いので一軒家でも駐車場の確保が出来ないという理由もあったのでしょう。
大体以上でしょうか?
食に関しては恐らく格差は殆ど無かったと思います。友人宅に遊びに行って出てくるおやつだって差は感じられませんでした。
でも殆どの家ではジュースが出てくるのに、弁護士の息子の家ではコーヒーが出てきてびっくりしたことがあります。
小学校2~4年生くらいにコーヒーを出すんですよ!
砂糖やミルクを入れても一口飲んだだけで「自分には飲めない」と感じましたが、そんなこと言えませんので黙っていましたけどね。
今も格差があると思いますが、昔ほど露骨なものは少なくなっていると思います。
自分の子供の学校や友人を見ても格差と言う差を見出すことは大変に困難です。
以前こんな話しを聞いたことがありました。
●経済的に苦しい家庭ほどそれを表に出さず子供には無理しても金を使う。
●給食費など「払えない家庭ほど払う」。
これらの話しは子供の友人の父母や知り合いのお母様が民生委員をやっていた経験からの話として聞きました。
たまに問題になる「給食費を払わない」というのはどちらかと言うと中流以上/富裕層だそうです。
経済的に払えないのであれば減額や免除の制度があるわけですしね。
自分の子供に対してはもちろん、私から見たまだ見ぬ孫やひ孫も贅沢な生活は出来なくても世間並みの生活が出来る事を祈念してこの記事のまとめとさせて頂きます。
スポンサーリンク
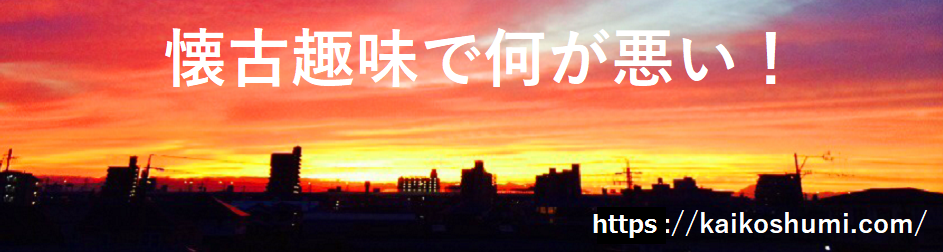
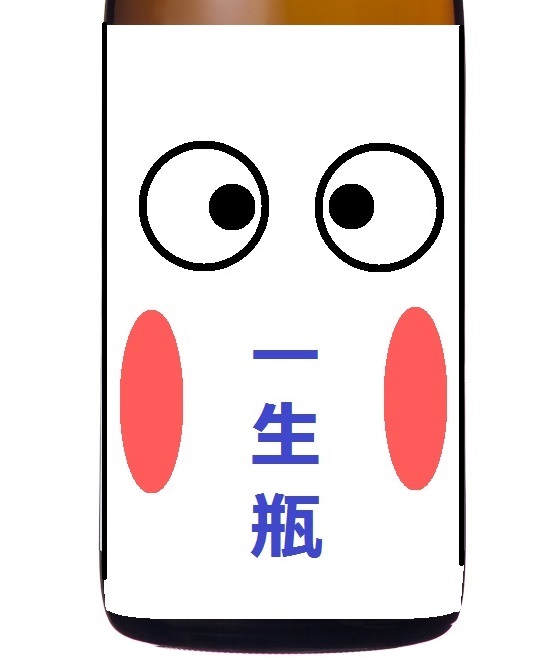
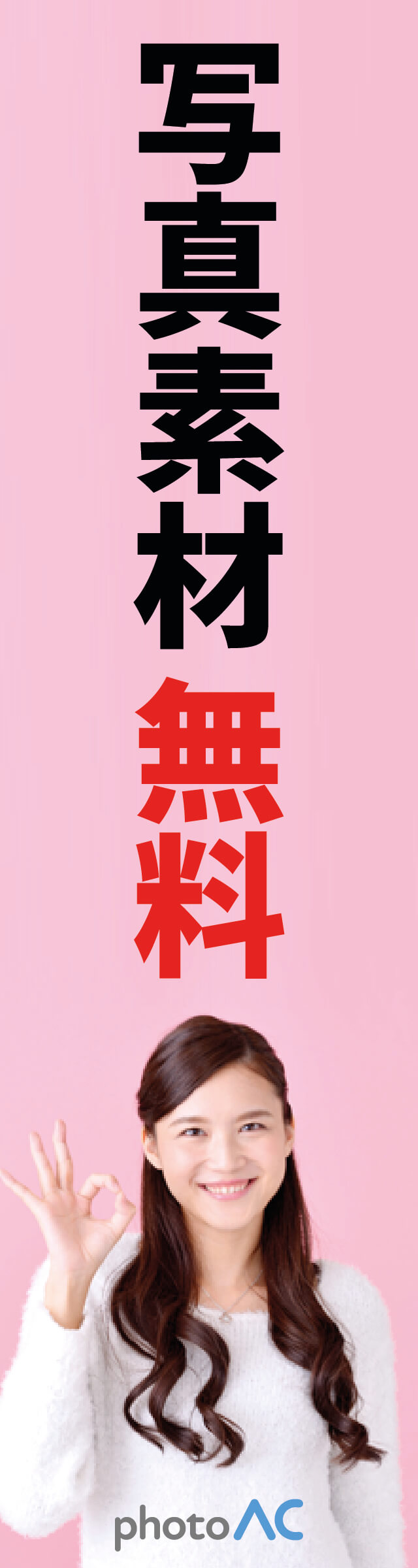


話は都営団地に住んでいましたが、公団との格差は大きかったです。
都営には、生活保護を受けている人や戦後日本に強制連行された人や 893 などもいてなどもいて、特にS50年代の頃にはかなり差があったと思うだべさ!
会長どうぞ!!! ピップエレキバン!!! 様
コメントありがとうございます。
公団(現、UR)と都営などの公営との格差は未だにあるようですね。
基本は公団だと「一定以上の収入」、都営だと「一定以下」となるようです。
でも公団もバブルの時に高級賃貸/分譲をたくさん作って、しかも民間よりもはるかに値段が高くたくさん売れ残ったり既に入居者がいたのに新規の人には大幅値引きをやって顰蹙を買ったのです。
公団というのは民間に比べるとメリットは大変に大きいのですが、でも民間との常識のズレは今でもあるようです。
住居に限らず結局日本も金持ちが支配する国になりつつあり、金を持った人間が生き残るのでしょうか?
金持ち=税金で食える人
貧乏人=民間人
この構図が完成されて一発逆転は無理じゃないかと思います。
かつては戦争や革命がそのチャンスだっだがもう無い。
今は起業しても10年持つのは1割です
9割が廃業して連帯保証の社長は貧乏人になります。
で初老の自分が親戚の子供にできることは
教育資金援助と失敗してもいいからチャレンジすることを説くことだけです。
戸山中14期 さま
コメントありがとうございます。
現実は仰るとおりだな、と思います。
それに特に近年金持ちになった人の多くは昔の血の滲むようなつらい労働を続けてやっとの思いで成功を勝ち取ったという人が少なく感じます。
もちろんどんな人でもつらく苦しい努力や散々涙して成功した人が今でもたくさんいます。
でも高々20代~30歳くらいでいきなり金をつかんでヘラヘラしているバーチャル金持ちとでも言うのでしょうか?
そういう人が増えています。
私はそれを全面否定をするつもりはないのですが、「これでいいのかな~?」、「努力って何?」と自問自答することがよくあります。
人によっては「経済格差は国の責任」と怒る人がいますが、結局資本主義国家ですので自分での努力しかありません。
でも一番大切なことは戸山中14期 様も仰るようにチャレンジ精神だと思います。
結果を気にしていたらチャレンジなど出来ませんものね。
我々もこれから先いくつになってもチャレンジ精神は忘れないようにしましょうね。100歳でも!
ご無沙汰しております。
私少し下の年代ですけど、格差ありましたねーど根性ガエルのヒロシの家(長屋)みたいのありましたよ。また林間学校だかに行く時に健康保険証の番号を記入するプリントを配られたのですが、「未加入世帯は未加入と朱書きすること」と書いてありましたね。あの頃まだ国民皆保険制度じゃなかったんですかねー子供だったのでわかりませんでしたが。
学習と科学はうちの校区では同級生のお母さんが戸訪して配ってました。どういう訳なのか聞きもしなかったのでわかりませんが、うちの母も1年位学習と科学配りやってました。いち早く手に入ったので私的には嬉しかったですが(笑)持ち回りだったのか小遣い稼ぎにやってたのか。
私が衝撃だったのは「ピザ」ですね。一軒家か長屋風アパートが主流のなか今でいう「マンション」の走りみたいな(4階建て位でしたけど)とこに住んでる友達いたんですよ。そこに遊びに行ったらおやつにピザ出て来て生まれて初めて食べてみたんですが「微妙」でした(笑)今みたいにドミノピザやマックが殆どない時代ですから、チーズとサラミの匂いが鼻についてあまり食べなかったら「左馬之助くんはあまり食べないのねー」と友達のお母さんに言われたのを鮮明に覚えてます。私は比較的遅い時の子だったので、うちの母は年代的にピザなんか知らない訳ですよ(笑)またその友達のお母さんはお姉さんじゃないかって位若かったですし。
左馬之助さま
コメントありがとうございます。
ご無沙汰です。お元気ですか?
さて、
・健保のこと
全然知りません。そんなことあったんですね。
日本は私が生まれた頃には既に「国民皆保険」になっていたと思っていました。
・科学と学習
お母様方には多少のお小遣いが入ったとは思いますが、これもやはり買えない子(家庭)への配慮だったのでしょうね。
人の親になり、自分の子供がそんなだったらと思うと今でも胸が締め付けられそうです。
・ピザ
子供の頃も嫌いではありませんでしたが、やはり一般的な食べ物ではありませんでした。
当然当時の子供の味覚と今の子供の味覚ではまるで違いますし、ぜいたく品だったのでしょうね。
またお越しくださいね。
(私的メールもお待ちしておりますよ)
以前コメントさせていただきました大久保の者です
懐かしく読ませていただいています
先日隣家の外構工事で当家の車両と事故がって揉めたときに、工事会社の社長が西戸山中出身の方で話がスムーズに進んでしまいました
(といっても年齢がとても上の方でしたが)
格差ってものすごかったかもしれませんね
子供の時分はそれに気づかず友達の家に行くのが楽しかった記憶があります。
自分の家は共同便所に風呂無しのボロアパートでした
友達の家でケーキを出されてびっくりした時代でした
ケーキなんてクリスマスか誕生日しか食べられなくて、自分のように日付が近いと年に1回です。
3時のおやつに甘い麦茶とケーキ・・・
あのカルチャーショックは死ぬまで忘れないでしょうねー
確かに公団とかってボロアパートに住む者からするとマンションに見えましたね
エレベーター付きの公団も珍しくなかったですしね
また当時を思い出すような投稿を期待しています
西戸山公園さま
こんにちは。コメントと再訪ありがとうございます。
あの時代の「格差」って大人になって振り返ってみると気がついた、というものばかりです。
当時は貧しいかどうかわからずただ毎日が楽しかった、それだけでした。
映画の「3丁目の夕陽」みたいに格差や低所得などの問題はあっても皆生き生きとして輝いていたということなのでしょう。
もちろん私は今でも輝いていると思っているし家族との時間もかけがえの無いものです。
でも幸せってお金や社会情勢では決まらないんだな、と思います。少なくても内乱/戦争/犯罪に巻き込まれなければどんな環境でも幸せなんだと思います。
ところで西戸山公園の脇に都営アパートがありましたね。地図で見ると今でもあるようですが、昔のは4階建てくらいの低層で、相当なボロボロでした。
そこに戸山中の美術の先生が住んでいたのです。
その先生は確か1年くらいで転勤してしまったのですが、当時20代前半くらいで【猛烈な可愛さ】でした!
何かにつけて同級生数人で先生の家に遊びに行ったのです。
多い時は男子と女子合わせて6人くらいで2K くらいの間取りのアパートに行って手料理をご馳走になりました。
その先生は絶対に怒らないし、画に描いたような可愛さで今でもポッとしてしまいます。
どうでもよい思い出話ですが、私は西戸山と聞くと真っ先にその先生を思い出すのです。
またご訪問くださいね。
新宿ネタだけだと厳しいですが、「あの時代、あの日」を思い出させる記事をがんばって書いていきますね。
私は巨人の原監督と同じ学年ですが、10年前に東横線の都立大学駅近くで全くの偶然で原辰徳本人を見た時は、余りの格好良さに本当にびっくりしました!さて此処からは私の子供時代の貧乏自慢?です。私は昭和34年1月生まれ、目黒区立原町小学校の卒業です。一学年が総計100名ひとクラスが30名強、入学の時、女の子はほぼ全員が、おかっぱ刈り上げ頭!私の妹もおかっぱ頭!そう云う時代でした。当時私の家庭は一塊の労働者に過ぎない父の少ない給料に依って支えられていました。私が1年生の頃、私を含めてクラスで2人だけが、就学援助を受けていました。これは給食費を一度支払うのですが、後で全額払い戻されたりクレヨン12色入りを無償で貰えたり、今考えれば、かなりオイシイ制度では有りました!私は極貧故に一年中いつでも同じ服を着ていましたしが、私の貧乏ぶりを馬鹿にする様なクラスメートは居ませんでした。62歳まで生き続けた現在、私の胸に去来するものは、人の本当の幸福とは、裕福で在ることでは無く、家族が真の愛で結ばれていること!自分が人として尊ばれること、自分にとって掛け替えのない大切な人が存在すること、これまでの幸運な出逢いに心から感謝できること!人生の歓びを数え切れない程感じられたこと!私は無神論者ですが自分の此れまでの人生に最高に感謝しています!人は人を幸せに出来る、自分にとって大切な人の幸せこそが私の最高の幸せです!心から自分の人生にありがとう。
6畳一間でも、本当に幸せだった様
こんにちは。コメントありがとうございます。とても共感出来ます。
所得が低い=貧しいではないと思います。
結局人間の幸せって精神文化なんです。
私は4年前に死の淵まで行って心臓手術をしましたし(本サイトのカテゴリ「イヤな思い出」→心臓バイパス手術、をご覧下さい。)
、昨年は人生の師ともいえる心底尊敬していた先輩をガンで亡くしてしまいました。
どんなに大金持ちになって、威張っていても人生は1度切り、という公平さは変わりません。
そしておっしゃるように人は人を幸せに出来ますし、他人からの一言で幸せにしてもらえることもたくさんあります。
人生は全てが素晴らしい、そのように私も考えて生きて行こうと思います。
またのご訪問お待ち申し上げます。
昭和42年の100円の価値。このコメントはアーム筆入れの記事に投稿すべきでした!ブログ主が直せる様でしたらよろしくお願い致します。
アーム筆入の方に移動いたしました。
「スパイ手帳」の記事もご覧下さいね。
管理人
ブログ主様。とするところを様。が抜けておりました。ブログ主様よりの返信を読んで。人とは自らが生まれ出る時代、国、民族、両親、性別まったく選択できません!生まれ出ることすら、そもそも自分の意思では有りません!さて私の出生時のエピソードですが、私は産婆!今なら助産師の手に拠って、この世に生み出されました。しかも時間は真冬の朝4時頃!しかも大難産で産婆ひとりでは足りずに父が、もう一人の産婆を探しまくって、やっと産声をあげたそうです!また小学校1年の時、先生がクラス全員に尋ねました。ひとにとって一番大切なものは何ですか?私以外の生徒が、ハイハイと手を挙げて次々に答えます!ある子は、お金です。と答えました。先生は幾つかの返答を聞いた後、手を挙げていない私に返答を求めました!私は確かな自信を持って大きな声で答えました!先生、人に一番大切なものは命いのちですっ!先生はハイその通りです。もしかすると?全員の称賛が有ったかも?私の人生は、これ迄出逢った方々に愛され支えられ続けて来ました。人生の全てに感謝します。最高の人生最高の幸運全てに本当にありがとう。
誠に御無礼致しました、様
コメントありがとうございます。
産婆さん、懐かしい名前です。今で言う助産師ですね。
産婆さんというのは医療資格はなかったのでしょうね。
助産師は正看護師免許を取った後にさらに1年学校に行って国家試験を突破する難しい資格です。
今は無資格の産婆さんなんて認められないでしょうね。
私が生まれたのは新宿歌舞伎町にあった日赤産院という病院でした。
近年まで存在し、今は駐車場になっています。
人生そのものが幸運、宝だと私も思います。
このような前向きの気持ちが幸せをもたらすのですね。
過去は変える事が出来ませんが、1秒前は全て過去、でも時々思い出に浸って心を休めるのが良いのでしょう。
そのために本サイトを作ったのです。
今後もよろしくお願いいたします。
【お願い】
これからもコメントは大歓迎ですが、投稿者のお名前を毎回変えるのはお控えくださいませ。
コメントを書く欄の上に「名前」という欄がございますが、ここが投稿者様のお名前を
ご記入いただく場所です。(もちろんハンドルネームでOKです)
ここに例えば「先ほどのコメント訂正です」などお書きになられると、当方には投稿された方の
お名前として表示されてしまいます。
当方でも混乱をいたしますし、また他のご訪問者様も混乱をいたしますので、「名前欄」には
ハンドルネームなどお名前をお書きになり、表題は本文の最上部にお書きくださいませ。
よろしくお願いいたします。